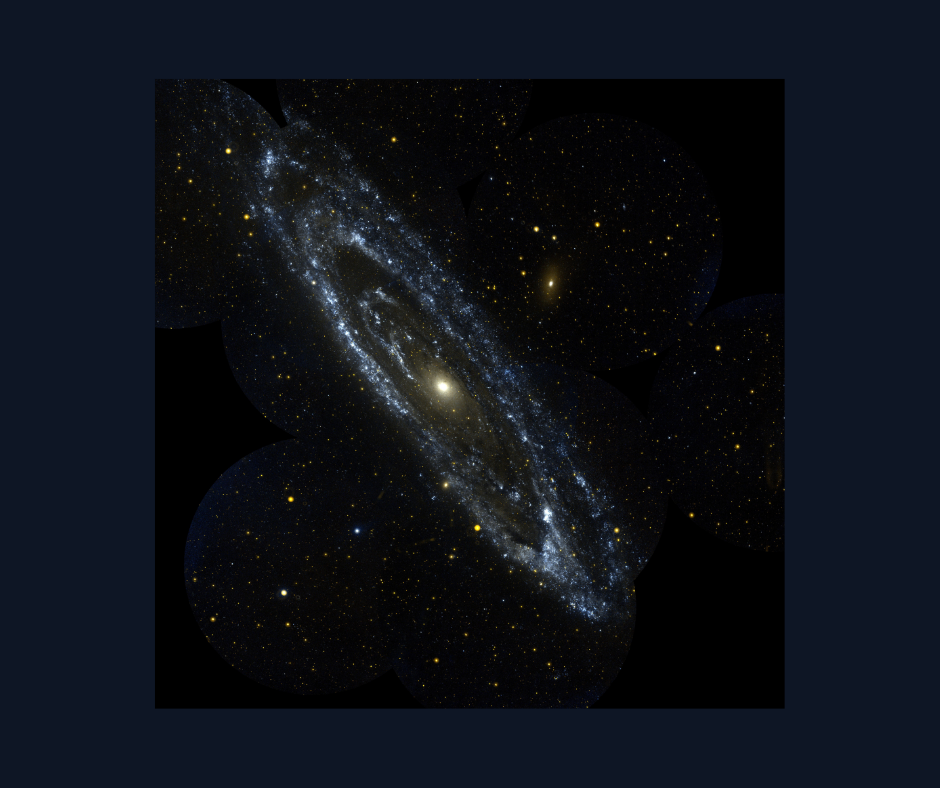死者の日 ヨハネ福音書6章37-40節「見えないものをー原主水をめぐって」巡礼と黙想会
2008年11月2日死者の日 ヨハネ福音書6章37-40節「見えないものをー原主水をめぐって」巡礼と黙想会、浜松にて
6:37 父がわたしにお与えになる人は皆、わたしのところに来る。わたしのもとに来る人を、わたしは決して追い出さない。
6:38 わたしが天から降って来たのは、自分の意志を行うためではなく、わたしをお遣わしになった方の御心を行うためである。
6:39 わたしをお遣わしになった方の御心とは、わたしに与えてくださった人を一人も失わないで、終わりの日に復活させることである。
6:40 わたしの父の御心は、子を見て信じる者が皆永遠の命を得ることであり、わたしがその人を終わりの日に復活させることだからである。」
今日は原主水のゆかりの地を巡って、巡礼をして、最後にここ静岡の教会でミサを捧げるというかたちになりました。原主水という人を想う時に、ほんとになにか、不思議な気持ちがするというか、なんていうんですか、非常に現代的というんですか、感じるところが多いです。先ほど見たように、古地図にですね、ちゃんと名前が出てるくらい、当時の浮き沈みの激しい、勝ち組、負け組がもろに出てしまう戦国の中で、結局は最終的には勝ち組に残ったというですかね、ほんとにどっちの殿様につくかで、没落したり、切腹したり、なにかそのようなものの中で、原主水は…もちろんお父さんは殺されてしまったわけで…というか、自害せざるを得なかったわけですが、彼自身はほんとに出世街道まっしぐらのような人生を歩みながら、結局はキリシタンであることを捨てなかったので、最終的に身体障害者になって、しかも、被差別部落という、江戸幕府の体制の中で最下層の人々とともに暮らすというですね、ほんとに劇的なドラマチックな人生を歩んだ人だということは確かだと思いますね。そういうのを見るとほんとになにか自分の心に問われるようなところがあるような気がします。
本を読んでですね、単に資料だけじゃなくて小説も読んでですね、彼のイメージが自分の中でいろいろ膨らんだり。まあ、でもそれを越えて、彼がなにを喜びとし、なにを悲しみとしたのか、そのあたりのことを非常に問われるような気がします。ある小説の中で、後書きだか前書きだったか…歴史小説というのは…司馬遼太郎の言葉ですけど、歴史上の人物を書くというのは、招魂…魂を招く…と、鎮魂、魂を鎮める、慰めるという、そういう意味があるというということを前書きだったか後書きだったかに書いてあって、実際死者の日というのはそういう日だと思いますね。日本のお盆なんかそうですが、西洋的にはそんなん考えないかもしれないですが、東洋的には死者の日というのは、先祖の魂が私たちのところに帰ってくる、だからいわゆる、霊を招き入れる、招魂というんですかね。で、まあ、お経唱えたり、お供え物供えたりして、霊を慰める。いわゆる鎮魂というんですかね。魂を鎮めて、そして帰ってもらう。そのようなものが、お盆というか、死者を弔うひとつの儀式というか、かたちになってるのであろうと思うんですね。で、この原主水の一生を、私たちがこうやって場所を巡りながら想うときに、やはり同じように原主水の魂が私たちのところに、この、帰ってくる。そして、彼からいろいろ力を得たり、考えさせられたり、というようなことをさせられてるわけですねでも、最終的に思うのは、私たちがこの、列福式を前にして、殉教者を記念したり、あるいはこうやって巡礼をしたりするのは、もちろんその招魂と鎮魂というですね、ふたつのこともあると思いますが、最終的には私たちが結局はどのように生きていくのかという、その問いかけを、なにか、もらうような、そのようなものではないかという気がします。原主水も非常に特徴的ですが、この188人の方々の、生涯、そして亡くなる時のことを想う時に、やはり、自分自身がなにを大事にするか、そしてなにを自分の根本にして生きていくかということ、それが非常に問われるような気がしています。ちょうど、この、今日の第二朗読がやはり特徴的なところで、コリント人への第二の手紙の4章ですね、「だから私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人が衰えても、私たちの内なる人は日々新たにされていきます。」と、あるんですが、これはもう、原主水見てたらそのとおりですね。外なる人、立身出世で、地位も名誉も、ある意味で、その当時のものを、もらえるものはすべて持っていたと思われますが、その、外なる人は、自分の体力も、それはすべて衰えていったわけですが、でも、私たちの内なる人は、日々新たにされていきます。うちなる人というものを原主水はあきらかに掴んでいたのはまちがいないと思います。多分、エリート侍というか、そのような時にはそういう内なる人のことまで思い至らなかったでしょう、というかんじですね。洗礼を受けていたでしょうけど、それほど熱心じゃなかったかもしれない。でも、ほんとに問われた時に、自分がいったいなにを大事にするのか、なにをほんとに賭けていくのかということをほんとに問われた時に、この、内なる人が日々新たにされている生き方を、彼はほんとに歩んだと思いますね。誰かの記録だったと思いますが、晩年の原主水は、自分で歩くこともできなかったけれど、なんて書いてあったのかな…至福の喜び…非常に大きな慰めを、彼は、天上の喜びを味わっていた、というような記述が出てきて、彼の内なる人は明らかに、日々新たにされていったのは、まちがいないと思うんですね。で、私たちの一時の軽い艱難は、まあ、殉教ということも一時の軽い艱難なのかもしれない。それに対して比べ物にならないほど、重みのある、永遠の栄光をもたらしてくれる。この、永遠の栄光というものを、原主水は見ていたでしょうし、私たちも、その、何か、比べ物にならないほど重みのある栄光に、私たちの人生というか、信仰生活の根本があるということ。それは殉教者の生き方が、あきらかに私たちに語りかけてくるような気がします。そしてやはりこの、18節ですね、「私たちは見えるものではなく、見えないものに目を注ぎます。見えるものは過ぎ去りますが、見えないものは永遠に存続するからです。」見えないものに目を注ぐ、それが私たちの本当の信仰の核心というか、私たちの、今生きてるなかでも、この、どのようにして見えないものに目を注いでいくかということかもしれない、というふうに思います。先ほどちょっと、徳川家康のところとか見て、まあ、なんというか、まだまだ徳川家康という人の存在というのは、ここでは大きい気がしますが、でも、結局、何百年、何千年したら、彼の名前も消えてしまって、駿河城も江戸城もみんなあとかたもなくなくなってしまう。結局は見えない物の世界の人ではないかという気がしますが、でも、原主水が見ていた世界は過ぎ去るものではなく、永遠に変わらない、そのようなものに向っていたのは確かだし、400年後に、こうやってもう一度、原主水が注目されることになって、やはり私たちがほんとに見えないものに向かっている、その価値の素晴らしさを彼が語ってくれているのではないかという気がします。私たちの日々の生活は、実際のところは、見えるものに振り回されて、まあ、いろいろ悩んだり、喜んだり、実際はしているわけですが、でもその中にあって、私たちも殉教者の視線というか、殉教者の眼差し、見えるものではなく見えないものに目を注いでいた、その、眼差しというか、視線をもって、私たちの生活を歩んでいけたらいいんじゃないかと思います。ま、経済がうまくいったりいかなかったり、戦争が起こったり、平和だったり、まあ、見えるものの世界ではさまざまなものがあるだろうと思いますが、私たちの根本はそこにはない。見えないもの、その恵みと力に支えられて生きている。その、殉教者の眼差しと心を、日々の生活の中で生きれるように、この、死者の日にあたって、今の生活を大事にしていけるように祈りたいと思います。
Podcast: Play in new window | Download