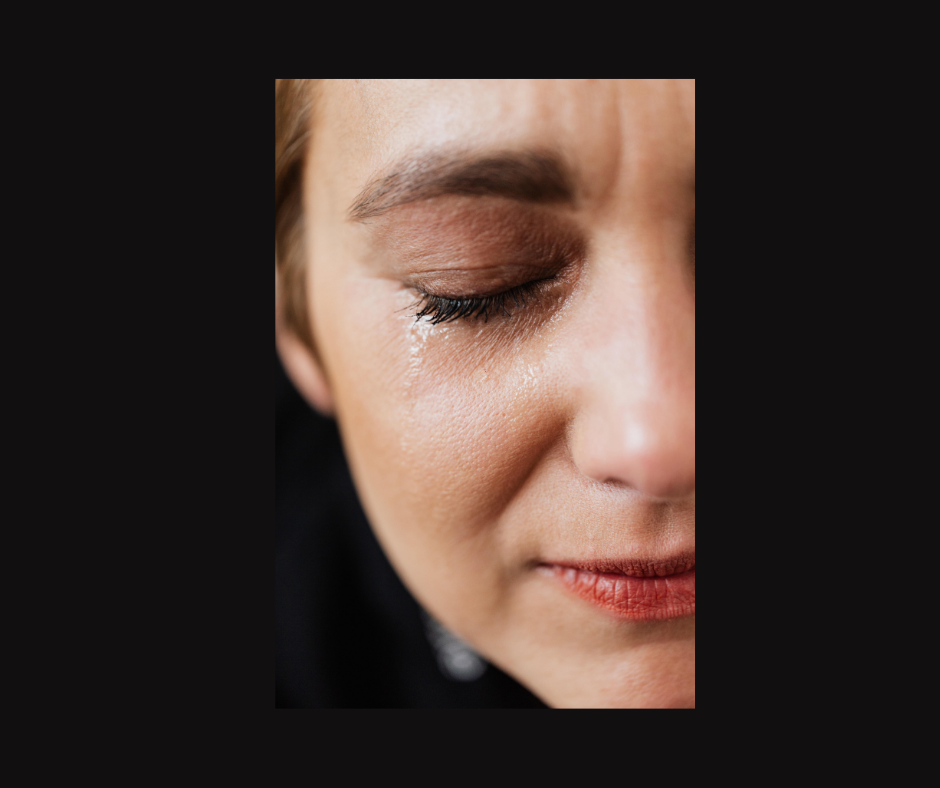【ミサ説教】ヨハネ福音書21章1-19節「苦しみののちに今」

ヨハネ福音書21章1-19節「苦しみののちに今」2025年 5月4日復活節第3主日のミサ カトリック長府教会
ペトロたちは夜通し苦労して漁をしても魚がとれませんでした。ですが、復活した主の恵みによって奇跡が起こりました。日本のキリシタンたちも多くの苦しみの中で殉教しましたが、死後長い年月ののち、今も私たちに希望を与えてくれます。これこそ主の復活のお恵みではないでしょうか。私たちも困難や苦労の方が多い人生かもしれませんが、必ずどこかで復活した主の力が働くときがあるはずです。

「津和野の乙女峠祭り」は盛況だったようですね!
福音朗読 ヨハネ福音書21章1-19節
1その後、イエスはティベリアス湖畔で、また弟子たちに御自身を現された。その次第はこうである。2シモン・ペトロ、ディディモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナ出身のナタナエル、ゼベダイの子たち、それに、ほかの二人の弟子が一緒にいた。3シモン・ペトロが、「わたしは漁に行く」と言うと、彼らは、「わたしたちも一緒に行こう」と言った。彼らは出て行って、舟に乗り込んだ。しかし、その夜は何もとれなかった。4既に夜が明けたころ、イエスが岸に立っておられた。だが、弟子たちは、それがイエスだとは分からなかった。5イエスが、「子たちよ、何か食べる物があるか」と言われると、彼らは、「ありません」と答えた。6イエスは言われた。「舟の右側に網を打ちなさい。そうすればとれるはずだ。」そこで、網を打ってみると、魚があまり多くて、もはや網を引き上げることができなかった。7イエスの愛しておられたあの弟子がペトロに、「主だ」と言った。シモン・ペトロは「主だ」と聞くと、裸同然だったので、上着をまとって湖に飛び込んだ。8ほかの弟子たちは魚のかかった網を引いて、舟で戻って来た。陸から二百ペキスばかりしか離れていなかったのである。9さて、陸に上がってみると、炭火がおこしてあった。その上に魚がのせてあり、パンもあった。10イエスが、「今とった魚を何匹か持って来なさい」と言われた。11シモン・ペトロが舟に乗り込んで網を陸に引き上げると、百五十三匹もの大きな魚でいっぱいであった。それほど多くとれたのに、網は破れていなかった。12イエスは、「さあ、来て、朝の食事をしなさい」と言われた。弟子たちはだれも、「あなたはどなたですか」と問いただそうとはしなかった。主であることを知っていたからである。13イエスは来て、パンを取って弟子たちに与えられた。魚も同じようにされた。14イエスが死者の中から復活した後、弟子たちに現れたのは、これでもう三度目である。
《15食事が終わると、イエスはシモン・ペトロに、「ヨハネの子シモン、この人たち以上にわたしを愛しているか」と言われた。ペトロが、「はい、主よ、わたしがあなたを愛していることは、あなたがご存じです」と言うと、イエスは、「わたしの小羊を飼いなさい」と言われた。16二度目にイエスは言われた。「ヨハネの子シモン、わたしを愛しているか。」ペトロが、「はい、主よ、わたしがあなたを愛していることは、あなたがご存じです」と言うと、イエスは、「わたしの羊の世話をしなさい」と言われた。17三度目にイエスは言われた。「ヨハネの子シモン、わたしを愛しているか。」ペトロは、イエスが三度目も、「わたしを愛しているか」と言われたので、悲しくなった。そして言った。「主よ、あなたは何もかもご存じです。わたしがあなたを愛していることを、あなたはよく知っておられます。」イエスは言われた。「わたしの羊を飼いなさい。18はっきり言っておく。あなたは、若いときは、自分で帯を締めて、行きたいところへ行っていた。しかし、年をとると、両手を伸ばして、他の人に帯を締められ、行きたくないところへ連れて行かれる。」19ペトロがどのような死に方で、神の栄光を現すようになるかを示そうとして、イエスはこう言われたのである。このように話してから、ペトロに、「わたしに従いなさい」と言われた。》
苦しみののちに今
イエス様が弟子たちに復活されて現れた。その3度目のエピソードが、このヨハネの福音書で語られています。ペトロがリーダーになって、弟子たちの主だった人たちと一緒に漁をしたのですが、結局、夜通し働いたけれども何もとれなかったという。苦しさというか、うまくいかない。そういうことがあって、その後、夜が明けて復活した主が現れて、そして復活した。主の言うとおりにするならば、たくさんの魚がとれたという不思議な、復活した主による不思議な大漁のエピソードですね。
実際、私たちの生活や働きの中で、何も夜通し働いたけれども何もとれないという結果が見えない、うまくいかないということもあるでしょうし、あるいは逆に、やはり復活した人の力が働いて、大きな恵みや力を与えられたというふうに感じることもある。実際は両方があるんじゃないかというふうに思います。
自分の司祭職を振り返ってどっちが多いかといったら、やっぱり夜通し働いて何もとれない時の方が多かったかなという感じはどうしてもしますけど、特に日本はそれほど宗教が流行らない時代になっていますから、それほど何かうまくいったという実感がないことの方が多いですけれど。
もちろん何か大きなお恵みや慰めや大きな実りを感じることも当然あるんですが、皆さん一人一人が振り返って、自分自身のですね、過去の、あるいは今の生き方の中で、神様から大きな恵みをいただいたなと思える時もあるでしょうし、どっちかというと何かうまくいかない、何かこう虚しくて苦しみが多かったというふうに感じることがあるかもしれない。
ある信者さんと話したら、もうほとんど苦しみですと言って苦しかったのが絶対多いと言うんですが、それは人によって違うかもしれないですが、でも、私たちが生きている中で出会う苦しみや、何か困難に出会うたびにでも思うのは、やっぱりキリシタンの人たちの苦しみに比べたらあまり大したことないということは、やっぱり思いますね。
もちろんいろいろはもちろんありますけれども。昨日は5月3日で津和野の乙女峠祭りに、ここの信者さん20人弱の人たちと一緒に参加いたしましたけれども、あまりに盛大で、僕は40年ぶりだったんですね。自分がイエズス会に入ったとき、修練者の時に参加しているんですが、その時はこんなに大きくて、それほど人が集まってなかったような気がしたんですが、40年後に参加して、特に今年は聖年だったせいか1500人は超えていたと思いますけれど、たくさんの人が集まって盛大な式を昨日やってですね、励ましをちょっと受けましたけど。
でもああいう迫害されている人々のことを考えた時に、やっぱり夜通し働いたけれども何も取れない、そのような苦しみの中にいたことはまず間違いないでしょう。とにかく長崎でですね、迫害があって、250年間、隠れキリシタンで7代ぐらいそれを守り続けていて、明治維新になって、明治政府になって、やっと外国から宣教師が来られて、カトリックのそれでやっと自分たちの宗教が認められるかと思うと、明治政府は結局その幕府の近況をそのまま踏襲していたので、いわゆる浦上4番崩れといって3000人以上の人が隠れてたんですけど、彼らが捕まってあちこちに送られてですね、そこで信仰を捨てるように迫られて、津和野には150人ぐらい、150何人が送られて、結局津和野では37人かな、殉教している。
250年間の苦しみでやっと解放されるかと。思ったよりもさらに大きな苦しみで、彼らがやはり苦しみに耐えている時に、やっぱり神の復活したお恵みのイエス様のお恵みで何かがうまくいくということは全く実感できなかったでしょう。実際的には、暗闇の中に次の暗闇が来たというかですね。
しかも信仰が試されるようなことがあって、殉教していく。彼らにとっては希望とか何か復活の力を見出すこともなく、だからといってがっかりしてたかどうかわからないですけれども。でもその中で亡くなっていく方が多かっただろうと思われます。
でも、その乙女峠の彼らの苦しむも150年後になる、150年ちょっとぐらいになって、1500人の者が人が集まって、彼らの生き方から励ますと力を受けている。150年後にそのような実りというか、力が多くの人に働いているということも、やはり復活した主の力が働いているからこそ、そういうことがあったとしか考えられないような気がします。
キリシタン時代の江戸の初期迫害の最後、江戸幕府の頃も、ペトロ岐部とかイエズス会の神父さんたちも殉教しているわけですが、今からもう400年ぐらい前になるんですが、彼らには復活した力を感じることもなかったでしょう。実際に250年間の迫害の始まるところでどんどん殺されていくだけで、皆さん方バラバラだというし。ペトロ岐部もですね、殉教する時に、まさか400年後に自分が福者になるとも思ってなかったでしょうし、まさか400年後に多くの人々を励ますような、何か力を与えるような存在になるとは全く思ってなかったでしょうけれども。
でもやっぱり復活した主の力が働くことによって、彼らが福者になり、そして多くの人の模範として輝いているわけですね。津和野のあの殉教者たちも多分今運動がされていて、そのうち福者になるんじゃなかろうかと思うか分からないですけども。やはり私たちに与えられている最大の恵みは、復活した主の力が私たちに働くということですよね。
本当に短いスパンで考えたら、私たちのやっていることは本当に意味があるのかなというか、何か生きがいのない、やりがいのない仕事をやっているように見えることもあるし、何かですね、実りがなかったり、なんて言うんですかね、これをやっていて本当にいいのかなって思うような、日々の小さな家族の世話であったり、様々な困難を小さなことを繰り返していくような単純な毎日を過ごすことの方が多いかもしれないですけど、でも、私たちが信仰を持って復活した主と共に生きていくならば、私たちの小さな奉仕、私たちの小さな犠牲、毎日毎日の小さな活動や働き、そのことを通して、やはり私が私たちに対して、あるいはもしかしたら私たちの子供とか、次の世代、あるいはもっともっと先の年先になるかもしれないんですけれども、でも、復活した主の力が私たちに働いている以上、私たちのささげる祈り、犠牲や働きは全く無駄に終わることはないということですね。
私たちはやっぱり将来に向かって、希望の巡礼者として私たちが歩んでいる今がいくらだめであったとしても、何か希望が見えないように感じたとしてもですね、分からない。全く将来、私たちの小さな祈りや働きが、将来大きな実りにつながっていくように、私たちに与えられている小さな役割を、祈りを、小さな犠牲を果たしていく中でこそ、復活の力が働くんじゃないかなと思いますね。
今日の福音書の最後は、とれた魚もあったんですが、イエス様がわざわざ朝の食事を用意してくださって、それで人が働いて苦労して何もとれなかったのに、イエス様と共に朝の食事をすることができた。それはやはり今から考えたら、ミサのエウカリスティアとかご聖体を分かち合う神秘を、そこでこそ私たちは復活の主に出会える、あるいは復活の種がいつも私たちに恵みを分かち合ってくださっているということのしるしだと思いますね。
今日も感謝のうちに自分の人生がうまくいってようがうまくいってなかろうが、あるいは波瀾万丈であろうが、平凡な毎日であろうがですね、やっぱりそれらすべてを感謝と祈りを捧げながら、主の祭壇を共に囲んで復活したイエス様の恵みを共に分かち合いたいと思います。
Podcast: Play in new window | Download